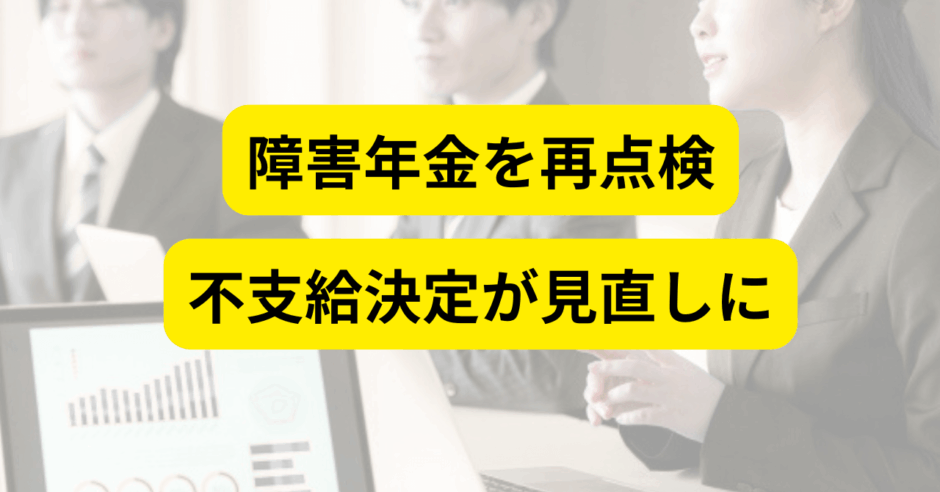こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、令和6年度の精神障害の不支給事案について、点検に関する進捗状況が公表されましたので、その概要をお知らせします。
障害年金 点検の背景
令和7年3月13日、共同通信から「障害年金、不支給が増加か」との報道が出ました。
その後も「幹部交代で厳格化か」「障害年金判定、判断誘導の可能性」などの報道が続いたことから、厚生労働省は、日本年金機構と連携して令和6年度の障害年金の認定状況についての抽出調査を実施し、その調査結果が令和7年6月11日に公表されました。
この調査結果と分析を踏まえ、適切な判定が行われているかどうかの点検(再調査)を行うこととなったのです。
なお、調査結果については下の記事で解説しています。
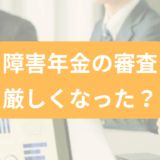 障害年金の審査は本当に厳しくなった?厚労省が調査結果を公表
障害年金の審査は本当に厳しくなった?厚労省が調査結果を公表
点検の対象者
点検(再調査)の対象者は、まずは令和6年度の精神障害等の不支給事案について優先的に実施することとなりました。
その後、精神障害に関しては、支給にはなっているものの下位等級に認定された事案についても順次点検を進めるとされています。
- 精神障害およびその他の疾患による障害(慢性疲労症候群、線維筋痛症など)について、不支給だった事案
- 精神障害について、目安より下位等級に認定された事案
- 精神障害について、目安が2つの等級にまたがるものについて下位等級に認定された事案
ちなみに、点検に該当する件数は以下のとおりです。
| 種類 | 令和6年度における件数(※1) |
|---|---|
| 精神障害(不支給) | 約10,200件 |
| その他の疾患による障害(不支給) | 約800件 |
| 精神障害(下位等級に認定) | 約25,000件 |
※1 審査請求に進んでいる事案を除く
これだけの件数を点検するのですから、それは大変な作業です。
点検の体制は、令和7年9月までは、高度専門職 1名、認定医5名、点検準備・集計業務等にあたる職員5名とし、10月からはさらに体制を強化(高度専門職プラス 1名、認定医プラス3名、職員プラス3名)して進めると報告されています。
現時点で124件が不支給⇒支給へ判定変更
令和6年7月までに不支給と決定されていた事案について、その点検結果が発表されました(令和7年9月19日公表)。
▼「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」への対応状況
https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/001565107.pdf
点検結果は以下のとおりでした。
| 点検済件数(R6.7原処分まで) | 支給となる件数 | |
|---|---|---|
| 令和7年9月19日現在 | 2,895件 | 124件(約4.3%) |
令和6年7月までに不支給と決定されていた2,895件のうち、点検の結果、124件(点検済のうち約4.3%に相当)について、いったんは不支給の決定を受けたものの、今回の点検で支給へと変更されることになりました。
不支給から支給へと変更になる方に対しては、支給決定通知書などの文書が順次発送されます。これは嬉しいお知らせですね。
今後も、年度内にかけて月2,000件程度のペースで点検を進め、その進捗状況は毎月公表するとされました。
公表ページは下記のとおりです。
▼障害年金の認定状況について|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tenken.html
判定変更になった理由とは
今回の点検で、当初の不支給決定を取り消し、新たに支給決定することとした理由として、以下の例が挙げられています。
- 【精神障害】当初は、症状の発現状況(陰性症状の有無、躁状態とうつ状態の期間、頻度等)を踏まえた日常生活の制限の程度を評価した。点検では、症状の経過や予後の見通し(療養が長期に渡っている、予後が悪い等)を踏まえた日常生活への影響をさらに重視した。
- 【知的障害】当初は、援助の必要度(慣れた環境下での状況、習慣的な動作が自立している等)を踏まえた日常生活の制限の程度を評価した。点検では、様々な環境を踏まえた援助の必要性(不慣れな環境下での状況、家庭内や職場内での支援状況等)をさらに重視した。
- 【発達障害】当初は、日常生活能力(家事、金銭管理、清潔保持等)や就労意欲を評価した。点検では、対人関係や意思疎通を踏まえた援助の必要性をさらに重視した。
- 【療養状況の観点】当初は、現在の病状や病状の改善状況を踏まえた日常生活能力を評価した。点検では入院歴(期間、頻度、状態が不安定かどうか等)、薬物治療の内容等(種類・量・期間)をさらに重視した。
- 【生活環境の観点】当初は、独居や福祉サービスの利用の有無などを踏まえた日常生活能力を評価した。点検では、その背景の状況(対人不信、対人恐怖、社会性の欠如、周囲の援助、IQ等)をさらに重視した。
- 【就労状況の観点】当初は、就労状況などを踏まえた日常生活能力を評価した。点検では、仕事の内容(単純作業の繰り返し、家業の手伝い等)、就労実態(配慮、勤務日数、職場での意思疎通等)、日常生活への影響(就労の疲労により日常生活で声かけが必要等)をさらに重視した。
なお、障害認定は、個々の診断書や申立書等の内容を踏まえ総合的に評価されるものですので、上記に記載した要素のみで判断しているものではないことに気をつけましょう。
今後の見通し
上で触れたとおり、日本年金機構では、今後も月2,000件程度のペースで点検を進め、その進捗状況は毎月公表するとされています。
また、障害年金の審査体制などを改善する方向性を打ち出しています。
令和7年9月時点の具体的な対応状況は以下のとおりです。
- 職員が作成する事前確認票について、職員による等級に関する記載を廃止。考慮要素の抜粋など客観的な事実のみを記載(R7.8月~)
- 認定調書は、不支給となる場合など、理由を丁寧に記載するよう、認定医に周知(R7.8月~)
- 理由付記文書は、より丁寧な記載とし、ルールを整備(R7.8月~)
- 認定事例は、判断のポイントなどを付した具体的な事例を作成し、職員と認定医に周知(R7.7月~)
- 全ての不支給事案について、複数認定医による審査を開始(R7.8月~)
- 新規請求について、審査をしない別の部署が無作為に認定医を決定する方式を導入(R7.7月~)
- 認定医に関する文書を廃止(R7.7月~)
- 障害認定審査委員会に福祉職の委員を追加(R7.8月の委員会から運用開始)
- 障害年金センター 405名⇒444名へ(R7.10月~)
- 日本年金機構 本部 障害年金グループ 9名⇒13名へ(R7.10月~)
今後も制度の公平性を確保し、障害年金を請求する方たちの権利が正しく守られることを期待しています。
参考リンク
障害年金の認定状況について|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tenken.html
2025年9月19日
「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」への対応状況|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/001565107.pdf
2025年9月19日
社会保障審議会年金事業管理部会資料(第80回)す|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo80_00003.html
2025年6月11日
「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表します|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00198.html
2025年6月11日
調査報告書概要(PDF)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001502248.pdf
2025年6月11日
調査報告書(PDF)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001502249.pdf