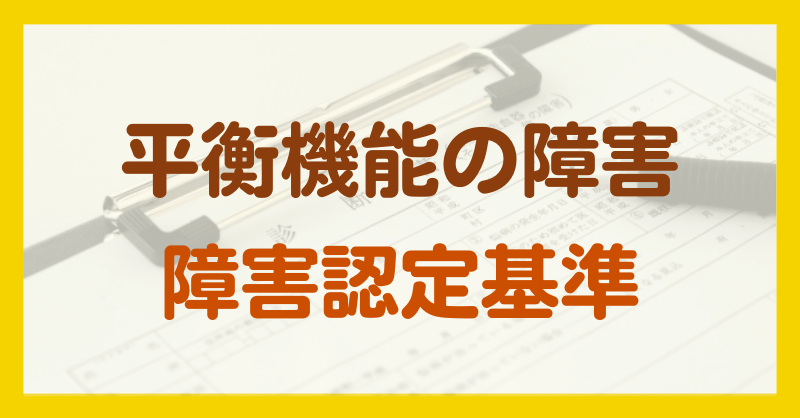こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。
このサイトでは、障害年金に関するさまざまな情報を分かりやすくお伝えしています。
今回は「平衡機能の障害」の認定基準の内容をご紹介します。
認定基準はどこに書かれているか
障害年金の「障害の程度」は、法と通知で定められた基準に基づいて認定されます。
具体的には、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に加え、厚生労働省が示す「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知により詳しい判断の目安が記されています。
このページでは、障害認定基準の中から「平衡機能の障害」に関する内容を取り上げて解説します。
平衡機能の障害の認定基準
平衡機能の障害についての認定基準は、次のようになっています。(障害認定基準をもとに、分かりやすく加筆修正しています。)
| 障害の程度 | 障害の状態 |
|---|---|
| 2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの。 具体的には、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能、又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行中断せざるを得ない程度のもの。 |
| 3級 | 中程度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの。 具体的には、開眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたときに、多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、どうにか歩きとおせる程度のもの。 |
| 障害手当金 | めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 (症状が固定していない場合は3級) |
※ 1級については基準が定められていません。
認定における留意点
平衡機能の障害には、原因が内耳性のものと脳性のものがあります。
それに合わせて、平衡機能の状態を記載できる診断書には、「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」と「肢体の障害用」の2種類があります。
平衡機能の障害のほかに併発している障害の状況に応じて診断書を選択しましょう。症状によっては両方の診断書を提出することを検討します。
対象となる疾病例
平衡機能の障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。
脳脊髄液減少症、外傷性脳損傷、脊髄損傷、外傷性脊髄空洞症、脊髄小脳変性症、小脳出血後遺症、小脳梗塞後遺症、メニエール病、多発性硬化症など
障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、「平衡機能の障害」の認定基準(原文)は下のリンクから見ることができます。
▼第3 第1章 第4節 平衡機能の障害|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-4.pdf
参考リンク
▼聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書を提出するとき|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-17.html
▼診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-17.files/02-1.pdf
▼肢体の障害用の診断書を提出するとき|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-18.html
▼診断書(肢体の障害用)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-18.files/03-1.pdf