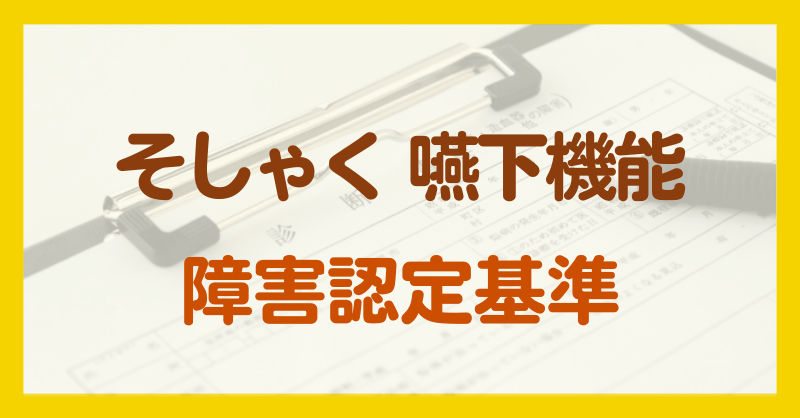こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。
このサイトでは、障害年金に関するさまざまな情報を分かりやすくお伝えしています。
今回は「そしゃく・嚥下機能の障害」の認定基準の内容をご紹介します。
認定基準はどこに書かれているか
障害年金の「障害の程度」は、法と通知で定められた基準に基づいて認定されます。
具体的には、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に加え、厚生労働省が示す「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知により詳しい判断の目安が記されています。
このページでは、障害認定基準の中から「そしゃく・嚥下機能の障害」に関する内容を取り上げて解説します。
障害等級
そしゃく・嚥下機能の障害についての認定基準(障害等級)は、次のようになっています。(障害認定基準をもとに、分かりやすく加筆修正しています。)
| 障害の程度 | 障害の状態 |
|---|---|
| 2級 | そしゃくの機能を欠くもの 具体的には、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取できないもの、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの (食物が口からこぼれ出るため常に手や器物等でそれを防がなければならないもの、または、1日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの) |
| 3級 | そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの 具体的には、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないため、ゾンデ栄養(主に鼻からカテーテルを通して直接胃の中に栄養を取り入れる経管栄養)の併用が必要なもの、または、全粥や軟菜以外は摂取できない程度のもの |
| 障害手当金 | そしゃくの機能に障害を残すもの 具体的には、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分にできないため、食事が制限される程度のもの (症状が固定していない場合は3級) |
※ 1級については基準が定められていません。
認定における留意点
- そしゃく・嚥下機能の障害とは、歯・顎・顎関節・口腔(舌・口唇・硬口蓋・頬・そしゃく筋等)・咽頭・喉頭・食道等の器質的障害や機能的障害によって、食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥(ごえん)の危険が大きいものをいいます。
- 障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって区分し、関与する器官・臓器の形態や機能、栄養状態なども十分考慮して総合的に認定されます。
- 歯の障害による場合は、歯の欠損部を補うため補綴(ほてつ)等の治療を行った結果により認定が行われます。
- 食道の狭窄、舌・口腔・喉頭の異常等による嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、摂取できる食物の内容によって認定されます。
併合認定について
- 「そしゃく機能」と「嚥下機能」にそれぞれ重複して障害がある場合でも、併合認定は行いません。
- 「そしゃく・嚥下機能の障害」と「音声又は言語機能の障害(特に構音障害)」が併存する場合は、併合認定の取扱いをします。
- 併合認定については次の資料をご覧ください。
▼併合等認定基準|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-2-1.pdf
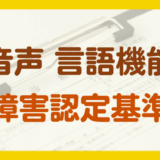 音声・言語機能の障害年金の認定基準
音声・言語機能の障害年金の認定基準
対象となる疾病例
そしゃく・嚥下機能の障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。
顎・顎関節・口腔・咽頭・喉頭の欠損、重症筋無力症、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症など
障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、「そしゃく・嚥下機能の障害」の認定基準(原文)は、下のリンクから見ることができます。
▼第3 第1章 第5節 そしゃく・嚥下機能の障害|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-5.pdf
参考リンク
▼聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書を提出するとき|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-17.html
▼診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-17.files/02-1.pdf