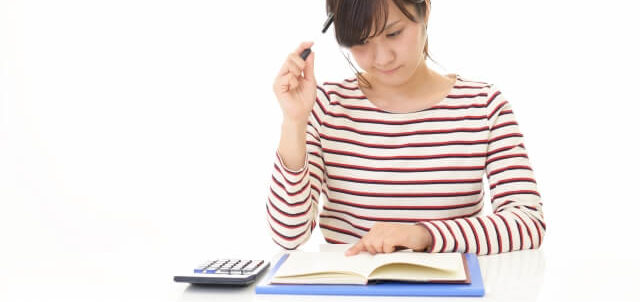こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、障害年金と国民健康保険との関係についてのお話です。障害年金の受給者にとって、毎月の国民健康保険料の支払いは大きな負担です。もし保険料が免除になるのならばとても助かりますよね。
そもそも国民健康保険とは
そもそも国民健康保険とは、公的医療保険の一つで、そのほかの公的医療保険には健康保険や後期高齢者医療などがあります。
国民健康保険は、無職の人、フリーランスや個人事業主、定年退職した人などが加入しています。
国民健康保険には被扶養者という考え方はなく、全員が被保険者となり、保険料は全額自己負担です。
ちなみに、サラリーマンが加入する健康保険の保険料は勤務先との折半で、被扶養者に該当すれば保険料の負担はありません。
障害年金の受給者であっても国保の保険料は免除にならない
結論から先に申し上げると、残念ながら、国民健康保険の保険料について障害年金の受給者であることを理由とした免除制度はありません。
障害年金の受給者であっても、決められた計算方法によって算出した保険料を納める必要があります。
ただし、下で紹介するように、保険料額を算出するにあたっていくつかの軽減措置があります。障害年金の受給者に限らず、要件に該当すれば軽減措置を受けることができます。
国保の保険料の算出方法
まずは、国民健康保険の保険料額がどのように算出されるのかを確認しましょう。
国民健康保険の保険料は、均等割・平等割・所得割・資産割などの合計です。
国民健康保険料=均等割+平等割+所得割+資産割
均等割は、被保険者全員に均等に割り当てられる額です。「一人当たり〇〇円」と計算されます。収入がない人にも割り当てられます。
平等割は、被保険者のいる世帯に対して割り当てられる額です。「一世帯当たり〇〇円」と計算されます。どの世帯にも平等に割り当てられます。
所得割・資産割は、所得や資産によって割り当てられる額です。「所得(資産)の〇〇%」という式で計算されます。所得や資産が多ければその分だけ額も高くなりますし、例えば所得がなければ所得割は0円という場合もあります。
なお、国民健康保険は都道府県と市区町村が運営しているので、自治体によって額や計算式が異なります。例えば、平等割や資産割は割り当てられない自治体もあります。
実際の計算方法は、各自治体のホームページをご参照ください。参考までに群馬県高崎市のサイトをご紹介します。
国民健康保険税について|高崎市
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700278/
保険料の負担軽減措置

国民健康保険の保険料額は、誰もが同じ額を負担する均等割・平等割と、所得や資産に応じた額を負担する所得割・資産割との合計額です。
この保険料額を算出するにあたって、いくつかの軽減措置があります。
資産割を課さない自治体もあるなど、細かい計算方法は都道府県(市区町村)によって異なりますが、以下の軽減措置は全国共通の内容です。
障害年金の額は所得から除外
「所得割」は所得に応じた額になっています。つまり、所得が多ければ「所得割」も高くなります。
「所得割」の計算の基礎とする所得とは、被保険者ごとの前年中の総所得金額等から基礎控除の43万円を控除した額の合計です。総所得金額等とは、給与所得、事業所得、雑所得、譲渡所得など様々な所得の合計額です。老齢年金などの公的年金に係る雑所得も、原則は所得に含みます。
しかし、障害年金の額は「所得割」を計算する際の所得には含めないことになっています。(※ このほかに、遺族年金や雇用保険からの手当等も所得には含めません。)
したがって、同じ額の現金収入がある人と比較すれば、障害年金の受給者は保険料額が低く抑えられることになります。
失業者等に対する軽減措置
障害年金を受給する人の中には、病気やケガによって退職を余儀なくされた人もいるでしょう。この場合、以下の2つの要件のいずれにも該当する人は給与所得を100分の30に減額する特例があります。
- 雇用保険受給資格者証で特定受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、31、32)または特定理由離職者(離職理由コード23、33、34)であることを確認できる人
- 離職時点で65歳未満である人
この場合、所得割を計算する際の所得が少なくなるので、「所得割」が低く抑えられることになります。
世帯所得による軽減措置
世帯主および同一世帯の国民健康保険加入者の所得の合計額が一定の基準以下の場合、「均等割」と「平等割」を7割~3割に軽減する仕組みがあります。
| 所得基準 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割 |
| 43万円+28.5万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 5割 |
| 43万円+52万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 2割 |
※ 所得基準の所得は、世帯主及び世帯に属する国保加入者の前年の所得の合計です。(世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主の所得を加算して判定します。)
※ 給与所得者等とは、給与所得を有する人又は公的年金等に係る所得を有する人です。
※ 減額判定基準日は4月1日です。ただし、新規加入世帯は資格取得日から適用されます。
※ 「所得割額の課税対象額」とは違い、基礎控除の43万円は控除しません。
この軽減措置を受けるには、世帯主と同一世帯の国民健康保険加入者が確定申告、または市県民税の申告(簡易申告を含む)をしている必要があります。したがって、収入がなくても確定申告(または市県民税の申告)を忘れずに行っておく必要があります。
なお、上記の申告が確認できれば自動的に判定されるので、保険料の軽減措置を受けるための申請は不要です。
どうしても支払いが困難な時は相談を
火災や天災などで財産に大きな損害を受けたり、本人や同居の親族の病気やケガなどで生活が著しく困難となり、預貯金等の利用できる資産を活用しても保険料の支払いが困難になった場合などには、申請によって国民健康保険料を減免する制度があります。
また、世帯主が東日本大震災により被災された場合や、世帯主が生活保護を受給している場合、国民健康保険加入者に在監者がいる場合も申請により国民健康保険料が減免される場合があります。
この他にも、市町村独自の軽減措置を設けている場合もあります。(例えば、未就学児の均等割額を軽減する制度など。)
特別な事情もなく保険料を滞納したり、相談がないまま滞納している世帯には、法の定めにより滞納処分等を行うことがあります。どうしても保険料の支払いが困難な時は早めに各市町村の担当課に相談しましょう。
関連リンク
全国健康保険協会|協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
国民健康保険制度|群馬県
https://www.pref.gunma.jp/page/3176.html
市町村国民健康保険における保険料の地域差分析|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/hoken.html